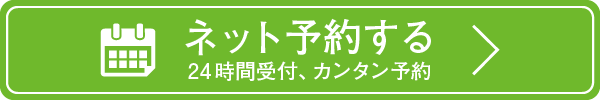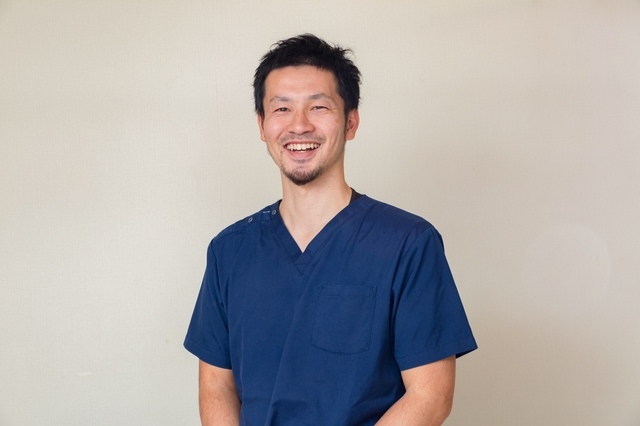慢性的な首、肩、腰など身体の凝り、張り、自律神経が乱れている方へ
はりいち鍼灸院
〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-1第二菊家ビル3階
都営三田線内幸町駅より徒歩3分 JR新橋駅・銀座線虎ノ門駅より徒歩7分
診療時間 | 平日 11:00~21:00 |
|---|
休診日 | 日曜日・水曜日・他不定休 |
|---|
完全予約制になります。
ご来院前にお問い合わせ下さい。
このような事でお困りではないですか?
- 腰のコリ、疲れ、痛みが目立つ
- 姿勢が気になる、歪んでいるのかも
- 足に痺れがある、長時間の座位、立位、歩行がきつい
- 痛めないように腰の状態を良くしていきたい
腰痛症とは

脊椎(せきつい)は、
頸椎(けいつい)、胸椎(きょうつい)、腰の骨の腰椎(ようつい)の17個の骨から成り立っています。
周囲にはクッションの役示す椎間板(ついかんばん)や
骨を支えている靱帯(じんたい)も重要な役割を占めています。
腰椎は首や背中の骨に比べて大きい構造となっており、
前弯と言い、骨がお身体の前に沿っているのが自然な形であり、
これを生理的弯曲(せいりてきわんきょく)と言います。
長時間立ったり座ったりするのは腰にストレスが溜まりやすいですが、この生理的弯曲があるからこそ衝撃を逃がすことが出来るのです。
しかし最近はデスクワークなど、無理な姿勢を保つことが多く持続すると腰椎の生理的弯曲が失われることが多いのです。
タイプとしては
・前弯の増強
これは生理的弯曲の状態が強くなってしまう状態です。
腰が反る様な姿勢で腰の部分が狭くなり、保つのが困難になってしまいます。
・後弯
これは生理的弯曲である前弯が失われ、腰椎がまっすぐに近い状態になります。
背中が丸まりやすく、背中の筋肉が疲れやすく凝りやすい、張りやすい状況に陥りやすいのです。
ここ最近ではデスクワーク、立ち仕事など、日常で動きが少なく、無理な姿勢を保とうとするため、腰痛に悩まされている方は非常に多いです。
腰痛といっても人によってタイプや原因は様々です。
下記に説明をしていきますので、ご自身は何が原因となって、どのタイプなのか?を理解していくと腰痛が良くなる近道になるかもしれませんね。
①筋肉が原因の腰痛
筋筋膜性腰痛(きんきんまくせいようつう)といいます。
筋肉とそれを覆っている筋膜という膜がありますが、腰の筋肉に過剰な負担がかかることで起こります。
主に関わりが大きい筋肉を紹介します。
※脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)
背中から腰にかけて走る長い筋肉です。
腸肋筋、最長筋、棘筋の3つから成り立っています。
主に背骨、姿勢の保持に関係しておりまっすぐ立ち続けていたり、座る姿勢を維持するのもこの脊柱起立筋が働いてくれているからです。
この筋肉が硬くなると、
座り続ける、立ち続けるのが困難になり、動作にも影響が出ます。
※腰方形筋(ようほうけいきん)
肋骨から骨盤にかけて走る少し奥の方にある筋肉です。
骨盤を安定させたり身体を傾ける(側屈)、後ろにそらす(伸展)に役立ちます。
この筋肉が緊張してしまうと、
身体の傾きを起こしやすくなり、バランスを崩しやすくなってしまいます。
※腹斜筋(ふくしゃきん)
お腹の横にあり、外腹斜筋(がいふくしゃきん)と内腹斜筋(ないふくしゃきん)の二つからなり、脇腹の表層、深層を支えています。
身体の中心となる体幹(たいかん)の保持や捻る動きの関わり、
呼吸の動かすときにサポートしてくれる役割も。
この筋肉が硬くなると、捻る動きに影響が出てしまいます。
※大腰筋(だいようきん)
最近はよく耳にすることが多いのではないでしょうか?
腰椎から足の骨の大腿骨(だいたいこつ)にかけて伸びているインナーマッスルです。
上記にあげた腰椎の前弯に関わり腰を正しい位置に納める役割が存在し、
立つ姿勢を正しい位置に保持することができます。
もう一つは足を引き上げる作用があります。階段を上るときにはこの大腰筋の働きで上ることが出来るのです。
この筋肉が硬くなると、足が上がりにくくなるために階段どころか平地でもつまづきやすくなります。
また大腰筋が縮こまるために腰椎の位置が変わることで、
反り腰やおなかが前にぽっこり出てしまう原因の一つにも。
②関節が原因の腰痛
椎間関節腰痛(ついかんかんせつようつう)といいます。
背骨と背骨の間が椎間、またその背骨をつなぐ関節を椎間関節といいます。
関節の近辺にはクッションの役割を示す椎間板(ついかんばん)や関節包(かんせつほう)、筋肉や神経が存在しております。
この関節に負荷がかかると痛みの元となる炎症(えんしょう)を引き起こします。
いわゆる捻挫(ねんざ)です。
関節に炎症が起きると、
痛み(歩くとき、寝返りを打つ、起き上がる、椅子から立ち上がるとき、ひどいときは座っていられない、立っていられないときも)が強く発症します。
炎症が起きている場合は触っていると表面が熱く感じるときもあるので、冷やした方が効果的です。
ぎっくり腰と呼ばれるのは、
筋筋膜性、椎間関節どちらでも起こる場合があります。
つまり筋肉、関節、どちらが原因としても気をつけなければなりません。
③椎間板ヘルニア
背骨と背骨の間には椎間板(ついかんばん)と呼ばれるクッションの様な役割を持つ物質が存在します。椎間板に反復して力が加わると、中にある髄核(ずいかく)と呼ばれる物質が外に押し出されます。
髄核が近くの神経を圧迫し、痛み、しびれを引き起こすのが椎間板ヘルニアの特徴です。
椎間板ヘルニアについて詳しくはこちら
④脊柱管狭窄症
脊柱管と呼ばれる背骨の間に走っている空洞の中に、神経が走っています。
この脊柱管が背骨の変形などで圧迫を受けることにより痛み、しびれ、歩行困難まで引き起こしてしまうのが脊柱管狭窄症です。
脊柱管狭窄症について詳しくはこちら
⑤坐骨神経痛
坐骨神経とはお尻から足の裏側や外側全体に分布されている神経です。
この坐骨神経が圧迫を受けることにより痛み、しびれ、足が冷える感じが出る方もいらっしゃいます。これが坐骨神経痛の特徴です。
坐骨神経について詳しくはこちら
そもそも腰痛はなぜ起こるの?

①日常生活の姿勢、負担の蓄積
座り仕事では、
・パソコンで目の位置が低く前屈みになりやすい
・時々足を組んでしまうことで腰をひねってしまう
・マウスを持つ手、モニターの位置などで身体の回旋が起こりやすい
立ち仕事では、
・調理などはキッチンで立ち続けると高さに合わせた姿勢で腰に負担がかかる
・美容師は曲がった状態でシャンプーなど腰に負担がかかる
・重い荷物を運ぶことが多いとき方は瞬間的に腰に負担がかかる
最近は仕事以外にスマートフォンを使用するケースが増えています。
電車で座っているときものすごく背中を丸めてみることもあれば、歩きスマホも無意識に身体が曲がっている方も。
かがむ姿勢がずっと続いた状態から腰を伸ばしてしまうのは困難です。
伸びづらいのを急に力を入れて伸ばそうとしてぎっくり腰になってしまうことも少なくありません。
②加齢
言いづらいですが、年齢に伴い徐々に周囲の機能は劣化していきます。
※筋力低下
年齢とともに筋力は落ちていきます、日頃の習慣で筋力を維持する人もいらっしゃいます。
20代の時と比べると60,70代は30%ほど落ちるともいわれているのです。
腰をまもるものとしてコルセット、骨盤ベルトがあります。
痛みが出ているときは支えとなってくれますが、長期使用は時に周囲の筋力を使用することがなく、低下を招いてしまうこともあるのです。
最近では在宅もありますよね、通勤は運動とまではいかないものの、デスクワークの方にとっては貴重な動く時間のはずです。
※骨の変形、骨量の減少
筋力も身体を支える一つではありますが、骨の問題も少なくありません。
特に女性の方は閉経とともにホルモンバランスなどにより骨密度が減少し、大きなけがではなくても骨折をしやすくなります。中でも高齢者に多いのが「腰椎圧迫骨折」といわれる腰の骨が骨折しやすくなるのです。
また、年齢に伴い、腰椎に関わる椎間板の弾力の低下、軟骨がすり減ってしまう、靱帯が骨化してしまうなど様々な変形に伴う要因が挙げられます。
腰以外にも股関節や膝の変形で二次的に腰がつらくなることもあるので注意が必要です。
③スポーツでの痛み
スポーツは心身ともにリフレッシュ出来るとても良い習慣であると思います。
本来であれば腰痛を解消するためにスポーツをするきっかけになる人もいるのではないでしょうか。
しかし、逆に腰痛を発症してしまう人も少なくありません。
アスリートでも手術を余儀なくされる方もいらっしゃいました。
そこで腰痛を引き起こさないためにはご自身での状態を把握することが大事です。
※自分のパフォーマンスを超えた運動をする
筋トレなどで自分があげられない重量を超えた重さでトレーニングするなどをすると痛めてしまうリスクは高まります。向上したい気持ちもあるかと思いますが、ご自身のお身体の状態に適した運動の負荷を選ぶのも大事です。
※体調が悪い中で運動をする
普段のお仕事で疲労が蓄積された状態などで運動をすると怪我のリスクが高まります。
疲労で血液循環が悪くなったり、風邪などの体調不良で体内に炎症が起こっている状態などは腰にも悪影響を与えやすくなりますので注意が必要です。
※反復した動きを続けた運動をする
ゴルフのスイングなどは一定方向に向かって腰を回旋させる動きとなります。
決まったところにストレスがかかりやすい動きを継続して行うことで身体にゆがみが生じやすくなり腰痛を引き起こすリスクが高まります。
これが続いていくと回旋がスムーズにいかなくなり無理にひねろうとして腰を痛めてしまう。
そのようなお声も聞いてきました。
スポーツも楽しく長く続けていきたい。
そのためには上記のような無理も考えてもいいのではないかと思います。
④柔軟性の低下、運動不足
今度は運動不足というところに焦点を当てていきます。
運動不足になるとどのようなリスクが起きてしまうのか
一つは筋力低下です。上記にも述べましたが筋肉は使わないと衰えていきます。
腰回りは特に筋肉で支えている役割が大きいです。一つ一つの筋力が落ちていくとさせられなくなりストレスを感じ痛みを引き起こします。
もう一つは筋肉が硬くなりやすくなります。
筋肉が硬くなるとどうなるでしょうか。
柔軟性がなくなり動きが制限されるたり、動くと痛みが生じやすくなります。
そうなると日常の何気ない動きにリスクが高まるようになり、
朝ベッドから起き上がる、会社の椅子から立ち上がるだけでぎっくり腰のような症状になりやすくなるので注意が必要です。
では上記の様な腰痛に対して当院ではどのようにして取り組んでいくか説明して参ります。
はりいち治療院の腰痛治療
※鍼灸治療
腰の緊張している筋肉、またはその緊張に関わる周りの筋肉
椎間関節腰痛では骨の間の椎間という部分に鍼を打っていきます。
緊張緩和と鎮痛効果を目的とした治療、また腰以外の箇所に鍼を打つことで
根本的な治療により近い治療が望めます。
・深部筋の緊張
腰がつらい時は背骨のすぐ脇が気になる事が多いのではないでしょうか?
基本お身体の筋肉は層になっており、腰にも比較的表面の箇所から深部まで筋肉が形成されており、特に深部はマッサージでは届きにくいため、終わった後は楽になったが、すぐ戻ってしまう。ということになりやすいのでしょう。
腰には腰方形筋という肋骨から骨盤につなぐ筋肉があり、この筋肉は腰痛はもちろん、お腹の痛みにも関係することがあります。
この腰方形筋を鍼でダイレクトにアプローチすることで、腰が楽になった。日常で辛くならなくなった。というお声も頂いております。
・お腹の筋肉
お腹には筋力トレーニングで鍛え上げる腹筋以外にも大事な筋肉があります。
それが大腰筋(だいようきん)です。
大腰筋とは腹筋よりも奥にあり、腰の骨と足の骨を結ぶ中心にある筋肉です。
この筋肉の役割は姿勢の保持に役立ち、縮こまると背筋をまっすぐするのが困難になります。
あなたの大腰筋はしっかり使えていますでしょうか?
鍼灸治療はこちら
当院はお陰さまでたくさんの患者様からありがたいお言葉を頂き、感謝申し上げます。
・脳梗塞後遺症に改善が見られた
・腰の痛み、しびれで動けなかったのが日常生活に支障がなくなった
・定期的にメンテナンスして風邪をひきにくくなった
・身体の歪みを修正して歩きやすくなった
・スポーツで痛めた肘の痛みがなくなり、今はスポーツを満喫できている
・腰痛がよくなり、できなかったゴルフを再開できている
・動悸の症状が改善した
・症状が良くなっても予防の為に通院している
その他多くのお声を頂いております。
お悩みが改善されない方、ぜひ当院へご来院お待ちしております。